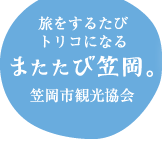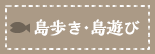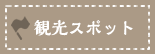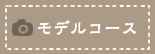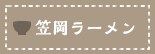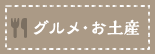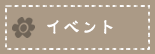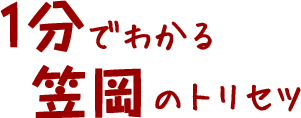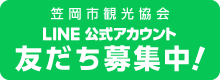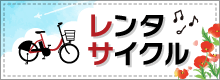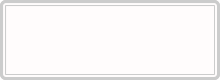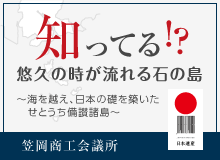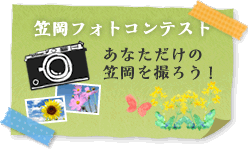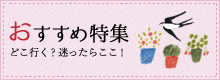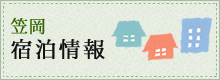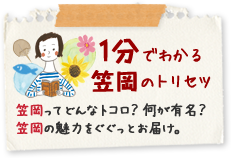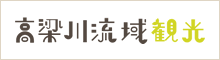![]()
笠岡ってこんなトコロ
キーワードで知る笠岡のキホン

岡山県の西南部に
位置する港町。
笠岡市は、瀬戸内海に面した港町で、沖合には、日本遺産にも登録されている笠岡諸島があります。観光地として有名な倉敷市や、広島県尾道市にも近く、周遊しやすい立地のよさも魅力です。

沖合には笠岡諸島が
広がります。
沖合の瀬戸内海には「ふるさと村」に指定されている真鍋島や、重要無形民俗文化財に選定された古式ゆかしい盆踊りが今も伝承される白石島など、個性豊かな7つの島々からなる笠岡諸島があります。素朴な島をめぐる島旅が、笠岡観光のひそかなブームです。

カブトガニが
シンボルです。
生きた化石と称されるカブトガニの繁殖地、笠岡。市内には世界で唯一のカブトガニ博物館が建ち、カブトガニに関する展示はもちろん、その研究も行われています。かぶとがに饅頭なる銘菓も販売され、市のゆるキャラもカブトガニ! まさにカブトガニが街のシンボルなのです。

岡山県屈指の花畑
として有名。
笠岡の魅力のひとつが、四季折々の美しい花スポット。山々や島々で、季節の花が彩りを添えます。なかでも干拓地の花畑は圧倒的なスケールを誇り、菜の花やヒマワリ、コスモスなどが無料で観賞できるとあって、開花を迎えると連日多くの人で賑わいます。

文化と歴史と、
見どころいっぱい。
郷土が誇る日本画家・小野竹喬の名を冠した美術館や、県下最古を誇る遍照寺の多宝塔など、文化的なスポットや歴史的名所が点在。花畑が隣接する「道の駅 笠岡ベイファーム」や、自然豊かな広域公園の「かさおか太陽の広場」などファミリーに最適なスポットも多いです。
もう少し詳しく
笠岡市は、岡山県の西南部に位置し、西は広島県福山市と隣接しています。
気候的には温暖で雨が少なく、地形的にも平野が少ないため、"水と土地を求めて"の歴史でした。
土地については、干拓や埋め立てを行うことによってまかない、特に平成2年3月には、広大な笠岡湾干拓地が完成し、大規模機械化農業の基地として期待されています。
水については、大きな川もないことから、夏の渇水時には慢性的な水不足になるなど、先人たちは大変苦労してきました。
しかし、笠岡湾干拓事業に伴い、倉敷市を流れる高梁川から導水管を引いてくることにより、全世帯(離島含む)に水道水を給水することができました。
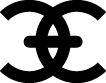
笠岡の市章
カタ仮名の「カサ」と、漢字の「笠」を図形的に簡便化し組み合わせたもので、弧と弧の交差は和を表し、両弧のひろがりは無限の発展伸長を暗示し、横一直線は力強い団結を象徴しています。

市の木
いちょう
(昭和47年4月1日告示)

市の花
菊
(昭和57年4月1日告示)

市のさかな
しゃこ
(平成14年4月1日告示)
笠岡のおいたち
原始
現在の市街地周辺は大部分が海であり、隅田川・今立川・吉田川などからの土砂の堆積により、陸地化したものと考えられています。
古代(古墳時代~平安時代)
古墳時代の5~6世紀には北川・新山に長福寺裏山古墳群をはじめとして古墳が築かれており、有力な豪族の支配下にあったことがわかります。
「笠岡」の地名は古代の「笠臣氏」の勢力範囲であったことによると言われています。
笠臣氏は吉備氏の一族で、大化の改新以後の国群制の施行により、笠岡地方はいくつかの群・郷に分けられました。
中世(鎌倉時代~室町時代)
鎌倉時代から室町時代には源平の動乱・南北朝の動乱でその名を残している陶山氏が勢力を持っていました。陶山氏は初め金浦に居を構えましたが、のちの笠岡へ移り笠岡山城を築きました。ここを拠点として、市街地を整備して、現在の笠岡の基礎を作ったといわれています。
陶山氏の没落後、戦国時代になると毛利氏の中国地方進攻とともに、笠岡は16世紀の中頃に毛利方の村上氏の支配となりました。村上氏は水軍を率いて活躍し、笠岡には笠岡城が築かれました。
現在の古城山公園はその城跡になっています。
江戸時代
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いの後は徳川氏の直轄地となりました。
その後、元和2年(1616年)に備中松山の池田氏、元和5年(1619年)には備後福山の水野氏の所領となり、延宝2年(1674年)には干拓により富岡新田が生まれ天和2年(1682年)に独立村となりました。
元禄11年(1698年)に再び幕府の直轄領となり、同13年(1700年)笠岡に初めて代官所が設けられ、以後幕末まで42代170年の代官支配が行われました。
これらの代官の中には「いも代官」として有名な井戸平左衛門や「敬業館」を設立した早川八郎左右衛門がいます。
近代
明治元年5月倉敷県に属しましたが、明治4年11月倉敷県が廃止され、備中一円と備後の一部とによって深津県が設置され、その管轄となりました。
翌5年6月7日に深津県は小田県と改められて、同県の県庁が笠岡に置かれました。
明治8年12月10日小田県は岡山県に合併されました。
当時笠岡は39ヶ村に分れていましたが、明治22年13ヶ村となり、同年6月1日町村制の施行によって富岡村を合併し、山陽線開通の年明治24年10月23日に町制を施行し、以後60年間、笠岡町は備中地方の産業・交通・文化の要衝として発達しました。
現代
昭和26年4月1日今井村を編入、翌27年4月1日金浦町と合併して市制を施行しました。
昭和28年10月1日城見・陶山・大井・吉田・新山・神島内の6ヵ村を編入、昭和30年4月1日神島外町・白石島村・北木島町・真鍋島村・大島村(柴木地区を除く)、さらに昭和35年4月1日北川村を編入して、面積117.9平方キロ、人口73,232人、16,604世帯の中都市となりました。