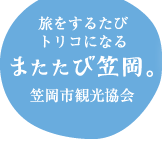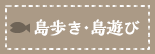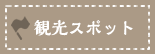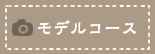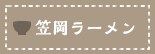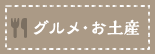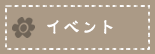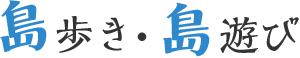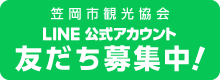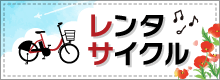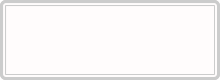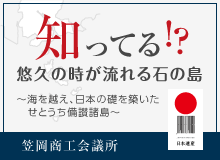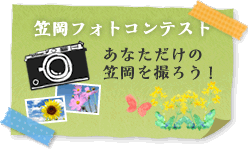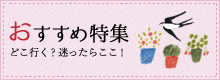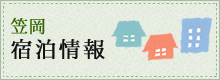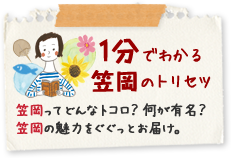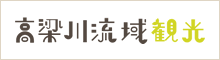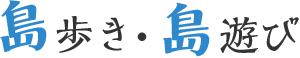
瀬戸内の風と恵みを感じて…
初めてなのにどこか懐かしい風景が待っている

笠岡諸島は岡山県の南西端の笠岡市沖にあり、瀬戸内海の中心に浮かぶ笠岡諸島は、大小31の島々からなっています。その内の高島、白石島、北木島、真鍋島、大飛島、小飛島、六島の7島が有人島で、島民の数は約750人から100人足らずまで、基幹産業も石材業から漁業・観光業など、それぞれに特色がある島が連なっています。
瀬戸内の多くの諸島は橋で結ばれている中、橋を一切有さず純粋に「離島」の風土を残す笠岡諸島は、心安らぐ落ち着いた空気に満ち溢れ、いつか忘れ去られた大事なものが沢山残っているような気がしてなりません。
各島へは、住吉港から運航している旅客船や高速船で行くことができます。また、白石島と北木島へは伏越港からそれぞれフェリーが運航しており、車やバイクなどを乗せて行くことも可能です。
引用:NPO法人かさおか島づくり海社ホームページ
島の紹介
高島(たかしま)
「漁師とつつじの島」
住吉港から約8km沖合の高島は、古くから瀬戸内海航路の要衝として栄えたといわれ、古事記に記されている神武天皇東征の際の高島行宮(あんぐう)が置かれた島、という説もあります。

白石島(しらいしじま)
「祈りとマリンスポーツの島」
周囲約10kmの笠岡諸島で2番目に大きい白石島は、古来有名な風光明媚の地であり、国指定の名勝にもなっています。
お盆に行われる国指定重要無形民俗文化財の「白石踊」は源平水島合戦の戦死者の霊を弔うために始まったと伝えられており、全国的にも非常に珍しい盆踊りで白石踊見学、体験ツアーも行われ多くの観光客が訪れます。

北木島(きたぎしま)
「石と流し雛の島」
島では北木石とよばれる極めて良質の花崗岩が産出し、その石を利用し大坂城や福山城の石垣や明治神宮神宮橋、靖国神社の大鳥居などが造営されたほどの名石です。現在でも採石と漁業が主な産業です。

真鍋島(まなべしま)
「歴史と映画の島」
住吉港から約18kmにある島で、島名は、真南辺の島、つまり備中国小田郡の南端にある島という意味で、後に真鍋の字をあてたと考えられています。
平安時代末期に藤原氏の一族が水軍の根拠地を置いて、付近の島々を支配下に治めていたという説や、源平合戦で平家方に属した真鍋氏の城趾や供養のために建てたと伝えられる石造宝塔などの史跡があり、歴史を今に伝える記録や史跡・行事の多さは、笠岡諸島でも随一です。

飛島(ひしま)
「潮待ちと椿の島」
住吉港から約18kmにある島で、一般的に大飛島・小飛島をあわせて飛島と呼ばれます。
笠岡諸島は古くから瀬戸内海の交通の要衝で、中でも大飛島付近は瀬戸内海の東西の潮が離合する場所といわれ、往来する船がこの地で潮待ちをしていたと考えられています。

六島(むしま)
「灯台と水仙の島」
住吉港から約22kmにあり、笠岡諸島最南端の島であるとともに、岡山県の最南端でもあります。
六島の南約4.5kmにある香川県荘内半島三崎との間は、潮流の速い海峡で、瀬戸内海を横断する大型客船などの重要航路となっています。この航路の安全を守るため、六島には岡山県で最初に灯台が設置されました。