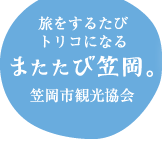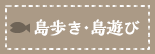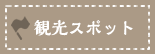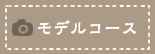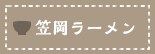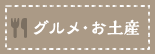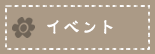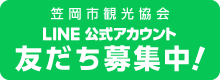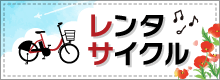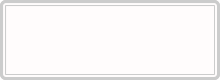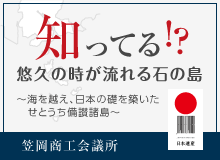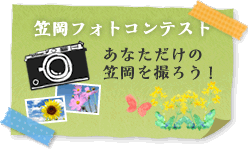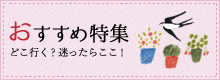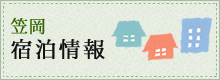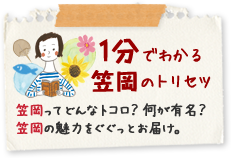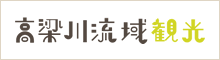井笠鉄道を偲びながら,ぶらり旅
(笠岡編・井笠鉄道記念館)
海岸沿いの町笠岡市と内陸部の井原市などを結んでいた井笠鉄道。1971(昭和46)年に本線が廃止されるまで,地域の重要な交通機関でした。その跡地をめぐります。今回は笠岡編です。

井笠鉄道の最盛期には,笠岡駅と井原駅を結ぶ本線,途中北川駅と矢掛駅を結ぶ矢掛線,井原駅と広島県の神辺駅を結ぶ神辺線の3路線がありました。
開業は1913(大正2)年で,その時の名前は井原笠岡軽便鉄道というものでした。1967(昭和42)年,当時の国鉄井原線の建設決定により,廃線が決まり,1971(昭和46)年に全線が廃線となりました。
その跡地は遊歩道になったり,井原鉄道井原線の路盤に転用されたり,また,笠岡市内部分の多くは区画整理などで消滅しています。
本線の飯山駅舎跡が井笠鉄道記念館として,一般公開されています。ただし決して交通の便が良いところではないので,訪問には乗用車が一番です。また,JR笠岡駅前からバスも運行(井笠バスカンパニー笠岡~矢掛線,新山停留所下車。下車後,西へ徒歩約10分)しています。
井笠バスカンパニー:笠岡~矢掛線時刻表(平日),(土・日・祝日)
観光スポット→井笠鉄道記念館
JR笠岡駅周辺

井笠鉄道・笠岡駅跡
JR笠岡駅と井笠鉄道・笠岡駅は同じ構内にありました。現在,井笠鉄道笠岡駅跡は駐車場になっています。
MAP

西ノ浜北児童遊園地
駅から歩いて5分ほどの所にある,西ノ浜北児童遊園地には当時の客車(気道車ホジ9)が保存展示されています。

平安橋周辺
笠岡駅を出発した井笠鉄道は,左手に山陽本線を見ながら隅田川を渡り,北へと曲がり隅田川沿いを北へと進んで行きました。この辺りは跡地は遊歩道になっています。また,街並みも古い笠岡市街の面影を色濃く残しています。
笠岡駅周辺の見どころは,徒歩で十分回れる場所にあります。駅近くの駐車場に車を止めてゆっくり回るのが良いでしょう。
- JR笠岡駅から約20分
- 山陽自動車道笠岡インターから矢掛方面へ約10分

笠岡市井笠鉄道記念館

旧新山駅舎
JR笠岡駅から車で北に20分ほどの所に,笠岡市井笠鉄道記念館があります。建物は大正2年に建築された旧新山駅舎。屋根部分を除けば,ほとんど当時のままの状態で保存されています。
展示室は元待合室で,井笠鉄道にまつわる様々な資料が展示されています。

屋外展示
1号機関車,客車(ホハ1),貨物車(ホワフ1)と鬮場(くじば)駅にあったターンテーブルが保存展示されています。1号機関車はドイツから輸入され,開業当初から昭和30年まで活躍していました。
客車内では,本線廃止日の最終電車運行ドキュメントDVDを見ることができます。
井笠鉄道の歩み
| 明治44(1911)年 | 井原笠岡軽便鉄道株式会社設立(大正4年に井笠鉄道株式会社と改称) |
|---|---|
| 大正2(1913)年 | 井笠本線(笠岡~井原)営業開始 |
| 大正10(1921)年 | 矢掛支線(北川~矢掛)営業開始 |
| 大正14(1925)年 | 高屋線(井原~高屋)営業開始 |
| 昭和15(1940)年 | 神高鉄道(高屋~神辺)を買収。路線総延長が37kmに。 |
| 昭和42(1967)年 | 矢掛支線と神辺支線(井原~神辺)の廃止 |
| 昭和16(1971)年 | 井笠鉄道本線(笠岡~井原)廃止 |
- 井笠鉄道記念から約5分

長福寺裏山古墳群

笠岡市走出・山口地区の境界部分の標高90mほどの丘陵上にある市内最大規模の古墳群です。古墳群は,前方後円墳,造出付円墳,円墳,方墳から構成されています。出土品などから5世紀代に築造されたと考えられており,なかでも双つ塚古墳は備中西部最大の古墳であり,吉備中枢をやや離れたこの地域に,急速に台頭した勢力の存在がうかがえます。